
昇給は、企業と従業員双方にとって重要なテーマです。
適切な昇給制度は、従業員のモチベーション向上と企業の成長に大きく貢献します。
しかし、昇給制度の設計や運用は複雑であり、人事担当者にとって悩ましい課題も多いでしょう。
今回は、昇給制度の種類から基準の策定、計算方法、よくある質問までを網羅的に解説することで、人事担当者の皆様の課題解決に少しでもお役立てできれば幸いです。
昇給制度の種類と特徴
🔸定期昇給とは
定期昇給は、年齢や勤続年数に基づいて、一定期間ごとに給与が自動的に増加する制度です。
日本では、年1回または年2回実施されることが一般的です。
メリットは、従業員にとって将来の収入が見込みやすく、生活設計を立てやすい点です。
一方、企業業績に関係なく給与が増加するため、業績不振時には人件費負担が大きくなるというデメリットもあります。
近年では、年功序列からの脱却を図る企業も増え、定期昇給制度を見直す動きもみられます。
🔸臨時昇給とは
臨時昇給は、業績好調時や個人の顕著な功績など、特別な状況下で実施される昇給です。
定期昇給とは異なり、時期や対象者が事前に定められていません。
企業にとって、優秀な人材のモチベーション維持や、一時的な業績向上への貢献を評価する手段として有効です。
従業員にとっても、自身の努力が明確に報われるため、大きなモチベーション向上につながります。
🔸ベースアップとは
ベースアップ(ベア)は、全従業員の基本給を一律で引き上げる制度です。
物価上昇や経済状況などを考慮して実施され、従業員全体の給与水準を引き上げる効果があります。
企業にとっては、固定費の増加という負担がありますが、従業員の生活水準維持や、労働市場における競争力向上に繋がるメリットもあります。
近年、人材不足が深刻化する中、ベースアップは人材確保・定着のための重要な施策として注目されています。
🔸その他昇給制度の概要
定期昇給、臨時昇給、ベースアップ以外にも、自動昇給、考課昇給、普通昇給、特別昇給といった昇給制度があります。
自動昇給は、資格取得や一定期間の勤務などを条件に給与が自動的に増加する制度です。
考課昇給は、従業員の能力や業績を評価して昇給額を決定する制度です。
普通昇給は、一般的な昇給を指し、企業の業績や経済状況などを考慮して決定されます。
特別昇給は、特別な功績や貢献があった場合に支給される昇給です。
これらの制度は、企業の規模や業種、経営方針などによって、採用されている制度やその内容が異なります。
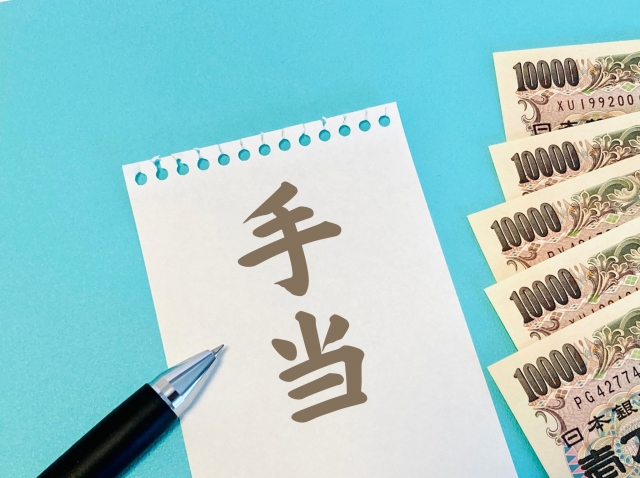
昇給基準の策定とポイント
🔸昇給に用いる評価指標の選定
昇給基準を策定する際には、まず、評価指標を明確に定義する必要があります。
評価指標は、業績、能力、貢献度、勤続年数など、様々な要素を考慮して選定されます。
ただし、指標が多すぎると評価が複雑になり、公平性を欠く可能性があるため、重要度の高い指標に絞り込むことが重要です。
また、各指標の測定方法についても明確に定める必要があります。
🔸評価指標の重み付けと調整
選定した評価指標には、それぞれ重要度が異なります。
そのため、各指標に重み付けを行い、総合的な評価を行う必要があります。
重み付けの方法には、様々な手法がありますが、企業の戦略や目標、従業員の特性などを考慮して決定する必要があります。
また、重み付けは、定期的に見直すことが重要です。
🔸公平性と透明性の確保
昇給基準の策定において、最も重要なのは公平性と透明性の確保です。
評価基準や重み付けの方法を明確化し、全従業員に周知することで、公平性を担保できます。
また、評価プロセスを透明化することで、従業員は自身の評価結果を理解しやすくなり、納得感を得やすくなります。
🔸昇給基準の明確化と周知徹底
策定した昇給基準は、全従業員に明確に周知する必要があります。
社内イントラネットや説明会などを活用し、基準の内容や評価プロセスを丁寧に説明することで、従業員の理解と納得を得ることができます。
また、疑問点や不明点があれば、すぐに質問できる体制を整えることも重要です。
🔸昇給基準の見直しと改善
昇給基準は、定期的に見直す必要があります。
市場環境の変化や企業戦略の変化、従業員の状況の変化などを考慮し、基準を適宜修正することで、常に適切な昇給制度を維持することができます。
見直しを行う際には、従業員からのフィードバックを積極的に取り入れることも重要です。

昇給額の計算方法とよくある質問
🔸昇給率の算出方法
昇給率は、昇給後の給与額と昇給前の給与額の差を、昇給前の給与額で割って計算します。
例えば、昇給前の給与が30万円、昇給後の給与が31万5千円の場合、昇給率は5%となります。
ただし、昇給率は、基本給のみを対象とする場合と、諸手当を含める場合など、企業によって計算方法が異なる場合があります。
🔸昇給額の算出方法
昇給額は、昇給前の給与額に昇給率を掛けて計算します。
例えば、昇給前の給与が30万円で、昇給率が5%の場合、昇給額は1万5千円となります。
ただし、昇給額は、昇給率だけでなく、個人の業績や能力、貢献度なども考慮して決定される場合があります。
🔸昇給基準に関するFAQ
Q1:昇給基準は、どのくらいの頻度で見直すべきですか?
A1:少なくとも年に一度は、市場動向や企業の業績、従業員の状況などを考慮して見直すことが推奨されます。
Q2:昇給基準に年齢や勤続年数は考慮すべきですか?
A2:年齢や勤続年数のみを基準とするのは、近年では不適切とされています。
能力や業績を重視した評価基準を構築することが重要です。
Q3:昇給基準に含まれる指標の数は、いくつが適切ですか?
A3:指標が多すぎると評価が複雑になり、公平性を欠く可能性があります。
重要度の高い指標に絞り込むことが重要です。
🔸昇給額に関するFAQ
Q1:昇給額に上限はありますか?
A1:企業によって異なりますが、財務状況や予算などを考慮して上限を設定している企業が多いです。
Q2:昇給額が低いと、従業員のモチベーションに影響しますか?
A2:昇給額だけでなく、昇給の理由や評価プロセスを明確にすることで、従業員の納得感を高めることができます。
Q3:昇給額の決定プロセスは、従業員にどのように説明すれば良いですか?
A3:評価基準や重み付けの方法を明確に説明し、個々の評価結果を丁寧にフィードバックすることが重要です。
🔸昇給手続きに関するFAQ
Q1:昇給手続きは、どの部署が担当しますか?
A1:人事部や給与計算担当部署が中心となって担当することが一般的です。
Q2:昇給通知は、どのような方法で行えば良いですか?
A2:書面による通知だけでなく、面談などを併用することで、従業員の理解を深めることができます。
Q3:昇給手続きにおける注意点は何ですか?
A3:公平性と透明性を確保し、法令を遵守することが重要です。
🔸昇給制度の見直しに関するFAQ
Q1:昇給制度の見直しは、どのくらいの頻度で行うべきですか?
A1:少なくとも数年おきに、市場環境や企業の状況、従業員のニーズなどを考慮して見直すことが推奨されます。
Q2:昇給制度の見直しにあたり、従業員からの意見をどのように反映すれば良いですか?
A2:アンケート調査や面談などを実施し、従業員の意見を積極的に収集することが重要です。
Q3:昇給制度の見直しにあたり、専門家のアドバイスを受けるべきですか?
A3:制度設計の専門知識が必要な場合、人事コンサルタントなどの専門家のアドバイスを受けることが有効です。
まとめ
今回は、人事担当者向けに昇給制度について、その種類、基準の策定、計算方法、そしてよくある質問までを網羅的に解説しました。
昇給制度は、従業員のモチベーション向上と企業の成長に直結する重要な制度です。
公平性と透明性を確保し、常に適切な見直しを行うことで、従業員にとって魅力的で、企業にとっても持続可能な昇給制度を構築・運用することが重要です。
昇給基準の策定には、評価指標の選定、重み付け、公平性と透明性の確保、明確化と周知徹底、そして継続的な見直しというプロセスが不可欠です。
昇給額の計算は、昇給率や昇給前の給与額に基づいて行われますが、個人の業績や能力なども考慮される場合があります。
様々なFAQを通して、昇給に関する疑問を解消し、人事担当者の皆様の業務に役立つ情報を提供しました。
当社では、企業ごとの運用実態や経営方針に合わせた「昇給基準の設計・見直し」を、労務・給与の実務と法令知識の両面からサポートしています。
画一的な制度ではなく、組織に根づく制度構築を目指し、就業規則や賃金規程の整備を通じて、社員の納得感と企業の公平性を両立できる仕組みをご提案します。
中小企業の人事労務に精通したスタッフが、制度導入から運用、従業員説明まで丁寧に対応いたします。